
高槻・島本 TOKK
Clouds
13.07
WEB版「TOKK」が「TOKK関西」にリニューアル
URLが変更になりました
検索する
閉じる

高槻・島本 TOKK
Clouds
13.07
25.11.25
津曲 克彦(がりさん)
鹿児島県生まれ。大阪府吹田市出身。龍谷大学国際文化学部(現:国際学部)を卒業後、新聞社や出版社、編集プロダクションなどを経た後、2015年からフリーライターとして活動。

「にぎわいの大阪」と「雅な京都」。この2つの大都市の間で、ひそかに、しかし確かな存在感を放つ町。それが、大阪府三島郡島本町です。
総務省の調査で「社会増加数(転入者から転出者を引いた数)」全国町村トップという驚くべき実績を記録したことは、新聞でも取り上げられました。令和3年(2021)には、民間調査による「住み続けたい街ランキング」で全国トップに輝いた実績も持つこの町は、外からも内からも高い評価を得ています。
アクセス、自然、子育て環境などのバランスを重視した「質の高さ」をめざす行政の取組と、町の根底に流れる「常温の温かみ」。そんな島本町への取材を通じて、町のビジョンを深く掘り下げていきます。
島本町は約17平方キロメートル、人口約3万人というコンパクトな町。
阪急とJRという二つの鉄道による「ツーウェイアクセス」で両都心への移動はスムーズ。ベッドタウンとしてこれ以上ない好立地を誇ります。

町の多くは緑豊かな山々に囲まれ、豊かな自然景観を形成。町内には環境省の名水百選に大阪府で唯一選ばれた「離宮の水」が湧き出ており、世界的ブランドであるサントリーの山崎蒸溜所がウイスキーの創業の地として選ぶほど、上質な水と自然に恵まれています。
都市の便利さと、古くから守られてきた自然の恩恵が調和する島本町は、住民にとっての誇りであり、住民の生活に潤いと安らぎを与えています。

そんな島本町の行政を担当する町役場で、まちづくりを担当する都市創造部次長(にぎわい創造課長)の佐藤成一さんと総合政策部政策企画課長の馬場田耕平さんに、なぜ社会増加数が全国町村トップに輝いたのか、理由を伺いました。

――社会増加数が全国でトップという快挙について、率直な感想をお聞かせください。
馬場田さん:町外のみなさまに評価され、居住地として選ばれることは大変喜ばしいことです。以前、住民の方々による投票で「住み続けたい街ランキング(いい部屋ねっと(大東建託)調べ)」で全国トップという評価をいただいたこともあります。
前回は住民の皆様からの評価、そして今回は町外からの評価として、島本町の名前が再び全国に伝わったことをうれしく思っています。人口が増えることで交通問題や保育所の待機児童対策といった行政課題も発生しますが、今回このような取材を受けるきっかけになるなど、町の魅力を知っていただく良い機会になったと捉えています。
佐藤さん:この町の魅力は、アクセスが良い一方で自然が非常に豊かであるという、その「絶妙なバランス」にあります。都市的な利便性と豊かな環境が両立している点こそが、多忙な20代後半から30代の子育て世代に支持されている最大の理由でしょう。

――社会増加数が増えた要因についてどのようにお考えでしょうか。
馬場田さん:現在にいたる流れを決定づけたのは、2008年のJR島本駅の開業です。これにより、JRと阪急の「ツーウェイアクセス」となり、大きく利便性が向上しました。また特に近年では、駅の山側、長年田んぼだった場所で行われた一体的なまちづくりによるマンションや戸建てへの入居が大きく貢献しています。
このまちづくりが単なる人口増加ではなく、子育て世代に支持されたことも、未来のこのまちを維持する上での重要なポイントだと考えています。

――転入者が増える中で、暮らしの質を維持・向上させるために、どのような具体的な取り組みをされていますか。
佐藤さん:私たちは、町の魅力を向上させるために「質の高いまちづくり」をめざしています。その象徴の一つが景観の保全です。
町は景観行政団体として、景観計画を策定しています。これは、歴史的な西国街道沿いの町並みや、町の背後に広がる山並みの景観を守るため「建築物の色彩やデザインにルールを設ける」という、きめ細やかな取り組みです。
また、都市計画的な手法として、市街化区域内の農地(生産緑地)を積極的に残し、都市と自然の調和を維持しています。
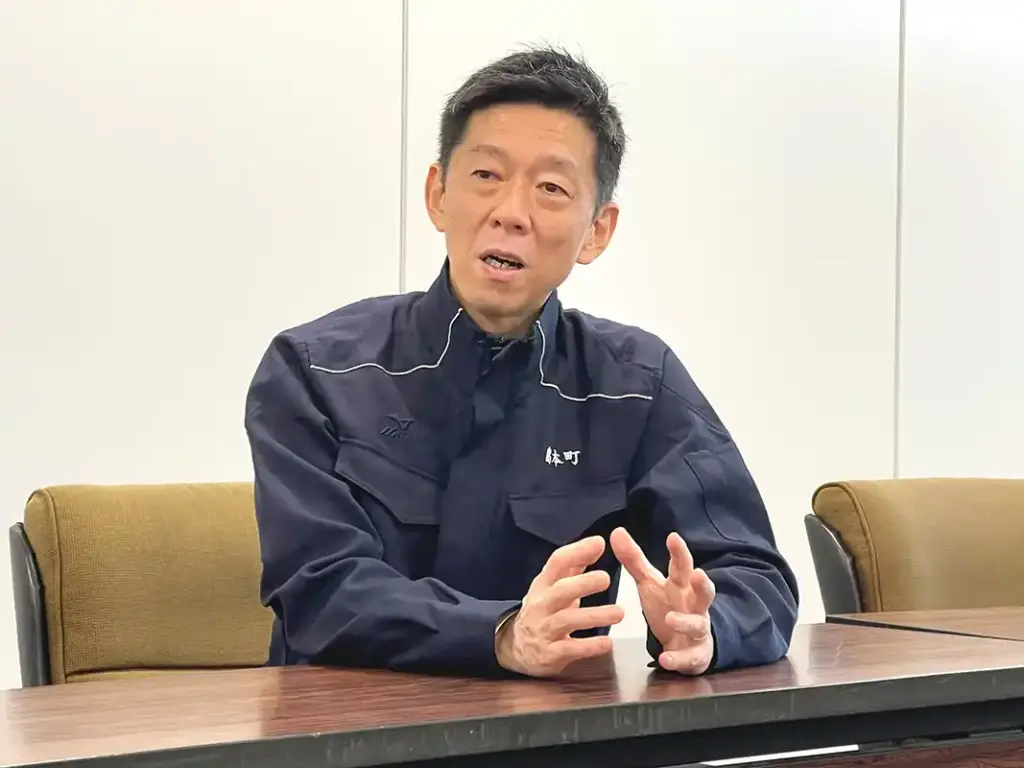
馬場田さん:人口増加に伴う課題への対応も重要な取組です。
新しく移住された子育て世代の増加により、小学校の教室不足という近年では珍しい課題も発生しています。これに対し、町では教育環境を守るため、「教育環境保全のための住宅開発に関する指導要綱」を制定しました。開発業者の方と協議し、開発時期や戸数の再検討、学童保育施設の整備などの検討をお願いしています。
そのほか、さまざまな取組を通じ、急激な人口増加に対する教育環境、生活の質の維持向上に地道に取り組んでいくことが重要だと考えています。
――子育てや日常の利便性についてはいかがでしょうか?共働き世帯の多いターゲット層には非常に重要です。

佐藤さん:日常の利便性では、町のコンパクトさが最大の強みです。駅と保育所、役場、図書館などが徒歩圏内に近く集まっていますから、共働きのご家庭でも、駅で降りてから子どもの送迎や役場での用事を無駄なくスムーズに済ませられる動線が確保されています。
これは、働く世代にとって時間の節約と精神的な負担軽減に直結する、非常に大きなメリットです。
――自然と調和した島本町ならではの「癒やし」も住民の方々にとっては魅力的ではないでしょうか。
佐藤さん:おっしゃる通りです。最も象徴的なのは名水百選の「離宮の水」。この良質な水と自然環境が、世界的なブランドであるサントリー山崎蒸溜所がこの地を選んだ理由でもあり、都会の喧騒から帰宅した人々に「ほっとする癒やし」を提供しています。
この「水の良さ」は、単なる資源ではなく、町の精神的な豊かさ、私たちが守り続けるべき宝です。
――住民の皆さんの町への愛着が深い理由、この町独自の魅力とは何でしょうか。その「島本愛」の源泉について、もう少し掘り下げてお聞かせください。
馬場田さん:個人的な感想ですが、町の「小ささ」に集約されるのではないでしょうか。
島本町は中学校2校区分の非常にコンパクトなまちであり、行政と住民の距離が近いことから顔の見える関係性を大事にしています。このような関係性を大事にしているからこそ、住民の方の声をお聞きし、きめ細やかなサービスにつなげていきたいという思いを私自身は持っています。
私の個人的なことですが、住民の方ともバンド演奏を通じたつながりがあり、そういった活動にもすごく楽しく参加させてもらっています。大きなまちにはスケールメリットなどを活かした大きなまちの良さがあると思いますが、島本町はこの「小さいこと」が最大の武器なんだと感じています。
佐藤さん:この町の感覚を表現するならば、「常温の温かみ」ですね。
大阪の持つエネルギッシュな熱気や、京都のようなクールな洗練さとは一線を画しています。その間のちょうどいいバランスの温度感が、日常の心地よさ、そして精神的な安心感につながっているのだと思います。なんとなく安心できる、無理なく自然体でいられる温かさが、この町にはあります。

佐藤さん: 住民の方との協働は、町の「癒やしの存在」を守る活動にも見られます。例えば、JR島本駅西側のまちづくりにおいて、希少なヒメボタルの生息地を保全区域に指定し、住民の皆さまがヒメボタルを守り育てる活動を主体的に行っています。水無瀬川でも多くのゲンジボタルを観察できます。

また大阪・関西万博では、地元の住民団体「SMALL」と行政が一体となってブースを出展しました。行政と住民の垣根が低いからこそ、地元のジビエやサントリーウイスキーといった特産品を通じ、町への「絆」や愛着がさらに深まりました。
住民一人ひとりの想いが、町の魅力として具現化される土壌が、この町にはあると実感しています。


――今回の社会増加数トップという結果を受け、今後、町はどのようなビジョンを描いていますか。
馬場田さん:このような結果になったからといって、無計画に人口増を追い求めることはありません。私たちがこれから取り組むべきは、過去に評価いただいたように、新しく来てくださった方にも心から「住み続けたい」と思ってくださるよう、生活の基盤をしっかりと整え、質の高い暮らしを維持することです。これが、次なるステップだと認識しています。
佐藤さん:長期的には、必ず訪れる人口減少社会を見据えて、私たちは「質の高いまちづくり」を身の丈にあった規模で続けていきます。令和7年(2025)3月には、無秩序な市街地の拡大を防ぐため、コンパクトな都市構造を維持すべく、都市機能誘導区域や居住誘導区域を定める立地適正化計画を策定しました。
また、建物のボリュームが増えすぎて住環境や景観が悪化することを防ぐための高さ規制の検討も重要です。これらの施策は、単なる「規制」ではなく、「町の個性を守り、未来の住み心地を保証するための仕組み」だと考えています。
私たちは、この「常温の温かみ」と「小ささ」という宝物を守り続けることが、未来永劫、この町が選ばれるための確かな戦略だと信じています。

私たちは、日々の忙しさの中で、「大都市の便利さ」と「豊かな自然」を両立させることは不可能だと感じがちです。しかし、島本町は、JRと阪急のツーウェイアクセスという現代的な利便性を最大限に活かし、同時に「名水百選の水」や「ヒメボタルの保全活動」といった具体的な「癒やしの存在」を守り抜き、その両立を可能にしています。
「常温の温かみ」という、無理のない、ちょうどいい温度感が息づく島本町。この町は、私たちに、「本当に質の高い暮らしとは何か」という、幸せの座標を静かに示してくれているのかもしれません。
ライター
津曲 克彦(がりさん)
幼い頃から移動といえば「阪急電車」。マルーンカラーの車両とゴールデンオリーブカラーのシートにくるまれて育ってきた「阪急育ち」です。京都に行くときはもちろん、大阪梅田や神戸、お参りすることが多い清荒神までも阪急を利用するのがデフォルトです。でも、阪急沿線にはまだ降り立ったことのない駅もたくさん!TOKKでの取材を通じて、密かに「阪急全駅下車チャレンジ」を果たそうともくろんでいるのです。ウッシッシ。
おすすめ記事
おすすめエリア